
ぎっくり腰はよく耳にしますが、「ぎっくり背中」を経験したことのある人は少ないかもしれません。ある日突然、背中に「ビキッ!」と電気が走るような激痛に襲われ、日常生活に支障をきたすこともあります。
本記事では、ぎっくり背中の正体と原因、なってしまった時の対処法、そして再発予防策まで分かりやすく解説します。
1.ぎっくり背中とは?
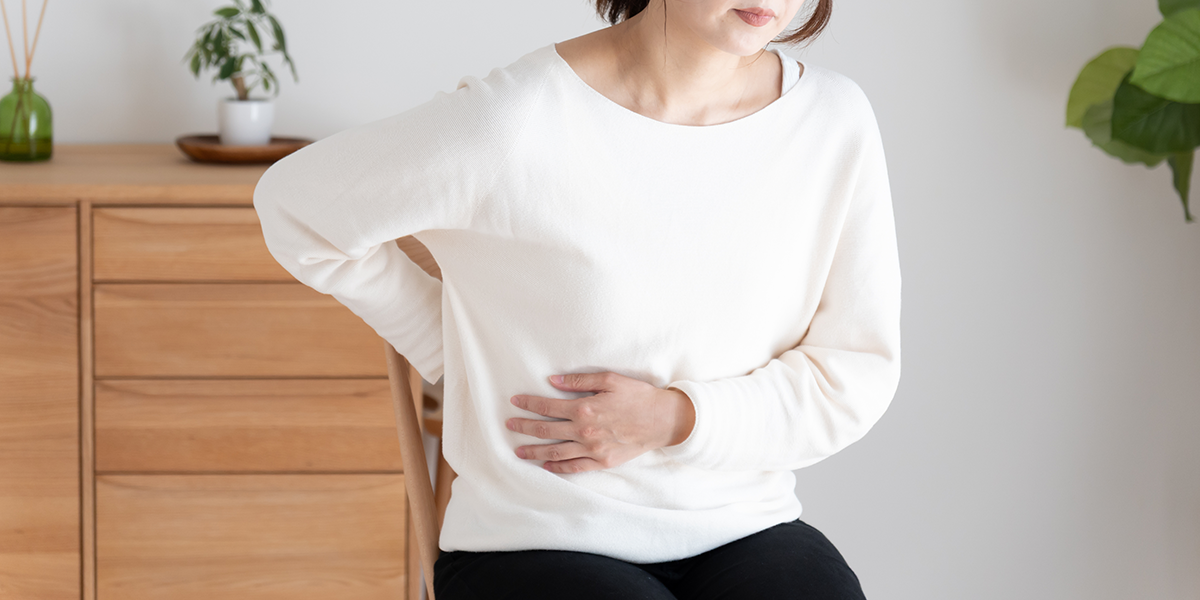
「ぎっくり背中」とは通称で、医学的には「筋・筋膜性腰痛」と呼ばれる症状に近いものです。背中にある筋肉や、それを包む筋膜、または靭帯といった組織が、何らかのきっかけで損傷し、強い痛みを引き起こす状態を指します。分かりやすく言えば、背中の筋肉が「肉離れ」や「捻挫」を起こしているような状態です。
ぎっくり腰が腰部(腰椎周辺)の痛みが中心であるのに対し、ぎっくり背中は主に胸椎(きょうつい)周辺、つまり背中の中央から上部にかけての筋肉に起こりやすいという特徴があります。
2.ぎっくり背中の原因

突然起こるぎっくり背中には、いくつかの要因が関係しています。急な動作だけでなく、日頃の筋力低下や姿勢の悪さが積み重なって発症を招くケースも少なくありません。
急な動作や反射的動作
ぎっくり背中の発症のきっかけとして最も多いのが、背中の筋肉に不意に大きな負担がかかる動作です。
具体的な例としては、以下のような瞬間があげられます。
- 重いものを持ち上げようとした瞬間
- 床のものを拾おうと中腰になった時
- 急に後ろを振り向いた時
- くしゃみや咳を勢いよくした時
- 寝返りをうった時
- ゴルフや野球のスイング、テニスのサーブなど、体を強くひねるスポーツ動作
背中の筋肉が対応できる準備が整っていない状態で、急に伸び縮みするような力がかかると、筋肉や筋膜はその負荷に耐えられません。結果として、筋肉の繊維などが傷つき、損傷を起こしてしまうのです。
筋肉の低下
運動不足や加齢によって背中の筋力や柔軟性が低下していると、ちょっとした動作でも負担が大きくなります。以前は問題なかった動きでも、筋肉が衰えていると支えきれず、損傷を起こすことがあります。
姿勢の悪さ
デスクワークやスマホ操作などで、長時間にわたって同じ姿勢を続けると、背中の筋肉は持続的に負荷を受け、ストレスが蓄積していきます。
疲労が溜まった筋肉は硬直し、血行不良を引き起こします。血流が悪くなると、筋肉に必要な酸素や栄養素が届かず、疲労物質が排出されづらくなる悪循環に陥ります。この結果、筋肉はさらに硬く脆い状態になり、ぎっくり背中を発症しやすくなるのです。
3.ぎっくり背中になりやすい人

ぎっくり背中は、特定の動作や生活習慣を持つ人に起こりやすい傾向があります。ご自身の習慣と照らし合わせながら確認してみましょう。
長時間同じ姿勢でいることが多い
デスクワーク中心の会社員、プログラマー、長距離ドライバー、あるいは趣味で長時間スマホやゲームをする人などは要注意です。
同じ姿勢が続くと筋肉が凝り固まり、血流が悪くなります。特に集中して作業をしていると、姿勢の崩れに気づかないまま筋肉への負担が蓄積してしまいます。
猫背や巻き肩など姿勢の崩れがある
日常的に、前かがみの姿勢、背中が丸まっている、肩が内側に入り込んでいる(巻き肩)、首が前に出ている(ストレートネック)といった姿勢の崩れがある人は、ぎっくり背中のリスクが高いと言えます。
こうした姿勢は、背中の筋肉に不自然な負荷がかかり続ける状態です。この日常的な姿勢不良が慢性疲労となり、ぎっくり背中のリスクを高めます。
運動不足
背中を支える筋肉や肩甲骨まわりを動かす筋肉が使われないと、柔軟性や筋力が低下します。その状態で、急に動いたり、重い物を扱ったりすると、筋肉や筋膜がその負荷に耐えきれず、損傷を起こしやすくなります。
急に激しい運動を始める
普段は運動不足なのに、週末だけ急にゴルフやテニス、草野球に参加する、あるいは年末の大掃除などで体を酷使する、といったケースも非常に危険です。準備運動が不十分なまま硬くなった筋肉を動かすと、一気に背中に負荷がかかり、ぎっくり背中が起こりやすくなります。
4.ぎっくり背中の対処法
痛みの程度や発症してからの時期によって、適切な対応が異なります。まずは状態を悪化させないための応急処置を行いましょう。
安定した姿勢で休息をとる
痛みが出た直後は、炎症が悪化するおそれがあるため、動かさず安静にしましょう。横向きで膝を軽く曲げ、背中を少し丸めた姿勢をとると、背中への負担を減らせます。仰向けが楽な場合は、膝の下にクッションを入れて膝を曲げると、背中が支えられて痛みが和らぐことがあります。
冷却する
発症直後で強い痛みや熱感がある場合は、炎症を抑えるために冷やすのが有効です。アイスパックや氷のう、氷を入れたビニール袋をタオルで包み、患部に15〜20分程度あてます。これを1〜2時間おきに繰り返しましょう。
ただし、冷やしすぎると血行不良を招き、かえって回復を遅らせることも。感覚がなくなるほど冷やしたり、長時間当て続けたりしないよう注意してください。
温める
発症から2〜3日経過し、ズキズキとした激しい痛みが少し落ち着いてきた時期には、冷やす方が効果的な場合もあります。
入浴、ホットパック、蒸しタオル、カイロなどで患部を温めることで血行が促進され、硬くなった筋肉がほぐれ、痛みの緩和や回復促進につながります。ただし、温めてみて痛みが増すようなら無理はせず、冷却に戻す方が安心です。
5.ぎっくり背中の再発を防ぐ予防法

ぎっくり背中は、一度経験すると再発しやすいと言われています。痛みが引いた後も油断せず、根本的な原因となった生活習慣を見直すことが重要です。
ここでは、ぎっくり背中の再発を防ぐための3つの予防法を紹介します。
ストレッチを習慣的に行う
背中や肩甲骨、胸まわりの筋肉を柔らかく保つストレッチを習慣化しましょう。特に長時間同じ姿勢で作業した後や、お風呂上がりなど体が温まっている時が効果的です。
両腕を大きく回す「肩甲骨回し」や、両手を背中で組む「胸を開くストレッチ」、四つん這いで「背中を丸める・反らすストレッチ」などを数分行うだけでも、筋肉の緊張を防ぎやすくなります。
適度な運動を行う
ウォーキング、水泳、ヨガ、軽い筋トレなどで背中の筋肉を動かすと、血流が良くなり、疲れにくい体になります。運動を始める際は、準備運動とクールダウンを忘れずに行い、急な負荷を避けることが重要です。
姿勢を改善する
長時間座って作業することが多い場合は、デスクワーク環境を見直しましょう。椅子には深く腰掛け、骨盤が立ち、足の裏全体が床につくように椅子の高さを調整します。モニターは目線の高さかやや下に設定し、覗き込まないように意識しましょう。
日常生活でも、背筋を伸ばした状態で立つように意識するほか、スマートフォンを見る時は画面をなるべく目線の高さまで上げて持ち、首の角度を浅くするよう工夫が必要です。また、エアコンの効いた室内や冬場などは、カーディガンを羽織るなどして背中が冷えないように対策しましょう。
6.ぎっくり背中の悪化を防ぐには早めのケアを
ぎっくり背中は、日頃の姿勢の悪さや運動不足、筋肉の疲労蓄積といった「生活習慣のサイン」として現れます。悪化させないために、姿勢・運動・休息のバランスを見直してみましょう。
強い痛みが長引いたり、手足のしびれ・感覚異常を伴ったりする場合は、早めに整形外科や整骨院などの専門機関を受診するようにしてください。


